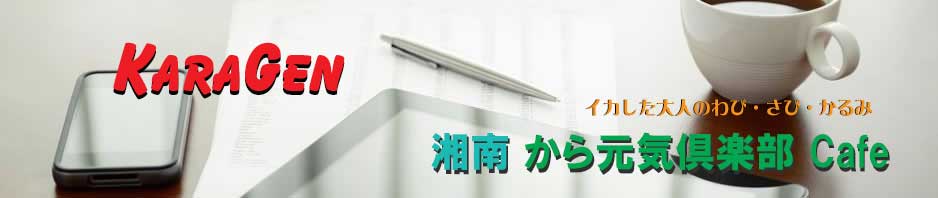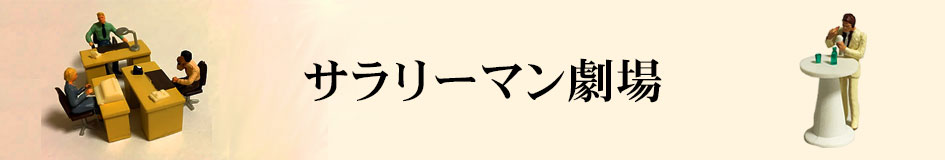
大森の「風に吹かれて」という店で、”風ふか寄席”っていう催しがありまして。そこでポニョの藤巻さんや”すみちゃんとステゴザウルス”の山田さんたちと、落語をやることになりまして、高座名が必要だろってんで”静鳩三郎”と名乗りました。

もっとも落語なんて、演じるどころか聴いたことさえ殆どなかったから、古典落語なんてできるわけがありません。仕方がないんで、創作落語をでっち上げました。
当日は山田さんに着物を借りまして、なにせ山田さんは、”柳亭風五”っていう本物の落語家さんでしたから。
帯はなかったんで着物の上からベルトをしめて、革靴を履きまして、まさにインチキ落語家にふさわしい和洋折衷っぷり。
ということで、そのとき作った創作落語のご紹介します。ちなみに翌年は、『渚の葬儀屋』っていうこれまたテキトーな創作落語をやりました。
★★★★★
演目「ぶぶ漬けいかがどす?」 (作:静鳩三郎[静炉厳])
秋でございます。秋の紅葉といえば、京都の嵐山なんてところが見事でございます。
さて、京都では、”お茶漬け”のことを”ぶぶ漬け”と言うそうですが、人様の家にお邪魔して「ぶぶ漬けいかがどすか?」と声をかけられても、「はい、いただきます」なんぞと元気に答えてはいけません。
これは、京都独特の文化、婉曲に帰りを促しているわけでして、 「とっと帰りなさい」ということなのでございます。
そんな”ぶぶ漬け”をお題にした「京の茶漬け」というお噺がございます。こういう話の流れであれば、そのお噺を披露するところでございますが、残念なことに、私、お話の内容はこれっぽっちも知りません。
そこで、きっとこんな話なんじゃないかなと想像した”京の茶漬け”をやらせていただきます。
*
(戸を叩く音)ドンドンドン ドンドンドン
「徳さん、徳さん、いるかい? ちょっと聞いてくれよ」
「(引き戸を開ける)朝っぱらからうるさいな。なんだい、八五郎か。冴えない顔してどうしたんだい?」
「いや、オレはねぇ。もう悔しくってしょうがないよ」
「はぁ」
「いや昨日ね、親戚の法事があってさ。京都に行ってきたんだよ」
「ほう、京都ね」
「で、せっかく京都に来たもんだからってんで、空いた時間になんか旨いもんでも食おうと思ってね。ぷらぷらと歩いてたんだよ。そしたら、通りのはずれにちょっといい感じの飯屋があったんだ。”平安京”って店」
「うん」
「入り口の横にね、”一見さんお断り”って張り紙があったんだけど、客商売なんだからいいだろうってんで、入ってみたわけ」
「なるほど」
「小奇麗な店内の壁には、筆で書いたお品書きがずらーっと並んでるのよ。でね、どれにしようかなって思う間もなく、年の頃なら35、6ってとこの女将がスッと出てきたの」
「うん」
「そんでさ、”おこしやす”…というかと思ったら、”ぶぶ漬けしかご用意できまへんがよろしいどすか”…てなことを言うんだよ」
「出たな! 京のぶぶ漬けか!」
「いや、オレだってさ。京のぶぶ漬けくらい知ってるよ。京都人にぶぶ漬けを食べるかって聞かれるってことは、さっさと帰れってことなんだろ?」
「で、大人しく帰ったのか?」
「帰ったよ。だって、厨房には下ごしらえした材料が並んでるし、食ってる客だっているんだよ。なのに悔しいじゃねーか。お断りならお断りって、ハッキリ言ってくれりゃいいんだよ.くぅうううう!」
「泣くな。おい、八五郎、泣くなって。オレもな来週、丁度、京都にいく用事があるんだよ。よし、お前のカタキをオレがとってやろうじゃないか」
「ほんとかい、徳さん」
「そんな上目使いにみるんじゃないよ。かわいくないんだから。まぁ、まかしとけって」
それから1週間ほどが経ち、徳さんこと徳次郎。京都の街角に立っております。
「えぇっと、たぶんこのあたりのはずだけど。あったあった! ここだよ、『平安京』ね。よさそうな店じゃないか。よし、入ってみるか」
(扉をあける)ガラガラ
「ほぉ、確かにいろんな料理のメニューが並んでるねぇ。あっ、女将が来た」
「お客さん、誠に申し訳・・・」
「まぁまぁ、わかってます。わかってますって。一見さん、お断りの店なんでしょう?」
「はぁ」
「お馴染みさんをお待ちになってらっしゃる?」
「はぁ」
「いや、あいにく、お馴染みさんと一緒には来れなかったんだけどね・・・」 と言いながら、徳次郎、鞄に手をつっこんで何やら取り出した。
「でも、お馴染みさんの代わりにこれをね、(と、ぶぶ漬けをとりだして)、ぶぶ漬けの用意をしてきたんだよ。いかがです?」 と女将に差し出した。
「ぶぶ漬け!?」
「そのとおり! 誇り高い真の京都人ならば、ぶぶ漬けをすすめられながら、図々しくその場に居座ることはできないはず! さぁ、ぶぶ漬けを食べて京都人を辞めますか? それとも、ここから去りますか?」
「くくぅ」
悔しさに唇を噛みしめる女将。徳次郎が追い打ちをかける。
「ぶぶ漬けを薦められても、この場に居座りますか? さぁ、さぁ! どうする!?」
涙を浮かべながら、荷物をまとめて店を出ていく女将。 徳次郎、首尾よく店の乗っ取りに成功。
「なんだ。意外と簡単にやっつけちゃったね、おっと、女将が戻ってきても店の中にはいれないように、入り口の前にはぶぶ漬けを並べてと。なんだか、京都人にとってのぶぶ漬けってのは、吸血鬼のニンニクみたいなもんだね、こりゃ」
店を乗っ取った徳次郎。 腹が減ったところで、近所のラーメン屋にでかけます。 カウンターでラーメンを食っていると店の電話が鳴っている。
店の主人は、トイレにでもいった様子。 そこで徳次郎、勝手に電話をとって調子よく出前の注文を受けると、これまた勝手にオカ持ちをもってイソイソと店を出ていきました。
「えぇっと、出前を頼んだのはと、ここだ。西園寺(さいおんじ)さんね」
(チャイム)ピンポーン。
「お待たせしました。来来軒でーす!」
奥の方から子供たちが走ってくる足音、そして声が聞こえてまいります。
「わーい。ラーメンラーメン」
(平戸を開ける)ガラガラ。
「ちわ、来々軒でーす。でぇもぉ! お持ちしたのは、ラーメンじゃありませんよ…ぶぶ漬けだーー!!!!」
「ぎゃーー! たすけてーーー!」
京都人である以上、ぶぶ漬けを奨められたら、その場を去るという不文律を破ることは許されな
い。 その掟には子供も大人も関係ないのだ。 破れば京都人失格だ。
一家でラーメンを食べるはずの楽しい夕べは、”ぶぶ漬け”の配達によって、家を追い立てられる悲劇の時間に変わってしまった。
子供達は全員トラウマだ。 そんな恐怖の出前がいく度も繰り返されます。 やがて、京の都は家を失った人であふれかえるのでありました。
だが悲劇はまだ終わらない。 徳次郎は、今度は市の職員を装って、腹を空かせた人々の前に現れては食料配給を行っております。 もちろん、配給する食糧は”ぶぶ漬け”に決まっております。
そして集まってきた人々に茶碗を差し出しながらこうささやくのです…。
「ぶぶ漬け食べますか? それとも、京都人やめますか?」
誇り高き京都人も、背に腹は変えられずに、ぶぶ漬けに手を伸ばす。 こうして、京都人の数はどんどん減っていった。 京都壊滅の危機である。
既に当初の目的をすっかり忘れてしまった徳次郎。 今では、すっかり京都の大地主となって、口調も怪しげな関西人風になっております。その日も、のんびりと露天の温泉に浸って、次の悪巧みを考えておりました。
「いやー、なんやいつの間にか、京都の大地主になってもうたな。こうなってみると、わてこそが、ほんまの京都人とちゃうやろか。でも、まだまだ終わらせまへんで。」 と、そこに後ろの茂みからガサゴソと音がする…と思いきや、突然、何人もの老若男女がわらわらと飛び出して、露天風呂を取り囲んだ。
それは、徳次郎に家を追われた人々の姿であった。
「なんやねん。誰かと思うたら、みなはんお揃いで、ぶぶ漬けでもいただきに来はったんですか?」
先頭に立った男が叫ぶ。
「ぶぶ漬けの用意なんていりまへん! なぜならぁ、これから、おまえ自身が、ぶぶ漬けになるからやーーー!」
その叫びと同時に、徳次郎を囲んだ男女は、それぞれが手にもっていた、お茶っぱ、アラレ、ワ
サビ、海苔、鮭の切り身などを、湯の中へと次々と投げ入れる。温泉は、瞬く間に、巨大なぶぶ漬けと姿を変えていった。
「ぎゃーー! ぶぶ漬けー!!」
既に京都人となっていた徳次郎は、ぶぶ漬けの湯にもがき苦しみながら沈んでいく。
「ぐぁああああ」
やがて、徳次郎の姿は湯の中に消えていきました。
徳次郎が退治されて、京の都に明るさと平和が戻ります。 そして徳次郎が沈んだ温泉は、誰が言うともなく”ぶぶ漬け温泉”と呼ばれ、京都の人は誰も近づかない温泉となりました。
それが転じて、全国的に「今度、温泉にでもいきましょう」という誘いの言葉は、今や、決して実行されることのない空約束の言葉になったということでございます。
おあとが、よろしいようで。
静 炉巌