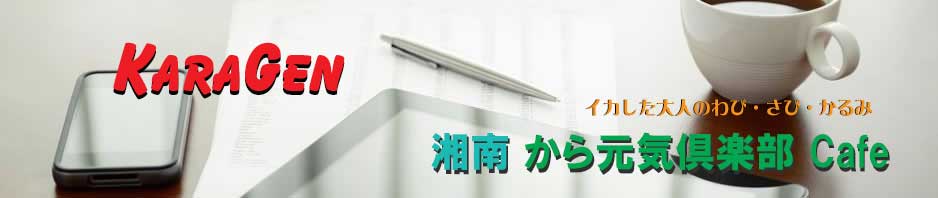鰻の専門店で食べる国産のうな重が好きなんだよ。だっておいしいもの。スーパーやチェーン店で得体の知れない鰻を食べるなんてとんでもない。
さて、鰻の焼き方には関東式と関西式があるのはよく知られたところ。
 鰻を背開きして、一尾を二つから三つに切って竹串を打ち、焦げ色をつけて焼いてから蒸し、タレをかけて焼き上げるのが関東式。
鰻を背開きして、一尾を二つから三つに切って竹串を打ち、焦げ色をつけて焼いてから蒸し、タレをかけて焼き上げるのが関東式。
頭つきのまま腹開きにして、長いまま金串を打って、蒸さずに素焼きにして、タレをかけて焼き上げるのが関西式だ。
関東式は柔らかく、関西式は歯ごたえがある。もちろん、どちらの焼き方もおいしい。
鰻調理の修行は「串打ち三年、割き五年、焼き一生」なんてことを聞くけれど、これは関東の話であって、関西では「割き三年、串打ち八年、焼き一生」になるらしい。
「串打ち」は、数本の串を”身の部分と皮の部分”の中間に均等に打つ。これができないと蒸した後などにスッポ抜ける。
特に一番串と呼ばれる左側の串は、メインで引っ掛けて持つからしっかり打たないとタレを付けて焼き終わる前に串から抜け落ちる。
「裂き」は、活鰻をエラの後ろ辺りを指で引っ掛けて2.3秒程度でまな板まで運び、半日から1日で200匹~350匹を失敗なく連続してスピーディに裂く修行。
 「焼き」は、関東や関西、あるいは店単位で焦がし加減や焼き加減が違うけれど、常に最良の焼き加減状態で細心の注意をして、お客様に提供する気持ちと技術の修行だ。まぁ、今は機械化されてるところも多いんだけどさ。
「焼き」は、関東や関西、あるいは店単位で焦がし加減や焼き加減が違うけれど、常に最良の焼き加減状態で細心の注意をして、お客様に提供する気持ちと技術の修行だ。まぁ、今は機械化されてるところも多いんだけどさ。
さて、おいしい鰻を最後の一口まで堪能したら、感謝を込めてのお勘定を支払う。
だいたい鰻は昔から高級な料理なのである。 だからこそ、夏場の売り上げ不振に悩んだ鰻屋に請われて、平賀源内が「本日土用丑の日」というキャッチコピーを考案したのだ。
江戸の初期には、鰻は下魚であり、ぶつ切りにして胴の端から串を刺し、蒲(ガマ)の穂のように焼いていた。この頃は棒手振りや屋台で一串16文(400円)で買えるマズくて安い庶民の食べ物だった。
ぶつ切りの蒲焼は、1800年頃には割いた蒲焼に変わり、味付けも醤油味の蒲焼が登場する。
天明年間(1781~1789)になると鰻専門の料理茶屋ができ始め、値段も一皿200文(5000円)になった。この頃から高級な食べ物になっていたのだ。
 文化年間(1804~1817)になると、鰻飯こと”うな重”が登場する。
文化年間(1804~1817)になると、鰻飯こと”うな重”が登場する。
大野屋という店で鰻飯一杯64文(1600円)で売り出されるが、飯の間に蒲焼を挟み、さらにその上に蒲焼を乗せた二段重の豪華さが評判となって、江戸中に流行したという。
鰻飯一杯が100文(2500円)、200文(5000円)の高級品も売りだされて、嘉永3年(1850)には、江戸市中に200軒を超す鰻の有名店があったという。
土用丑の日(7月20日、8月1日)ともなれば、毎年のように鰻の稚魚となるシラスウナギの漁獲量の低調から価格の高騰化と商売の不調が話題になる鰻だけど、そもそも鰻は大量消費する食材ではない。
”ちょっとした贅沢”のために鰻専門店にいく。そんな楽しみ方が鰻にはふさわしい。
Shang(2018/7/21)