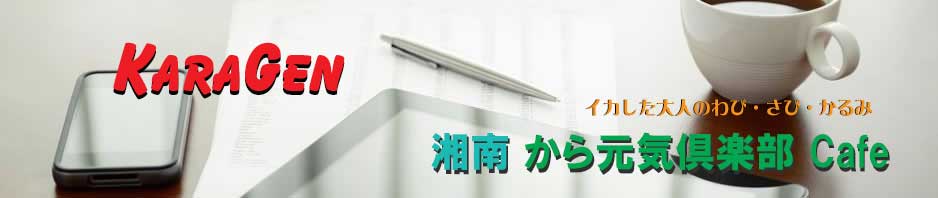この日、私と若松(わかまつ)は、秋田から上京してきたYくんたちと浜松町で合流して、江ノ島までドライブを楽しむことになっていた。Yくんは、腸弱会のサイトで知り合いになった若者である。
ハンドルを握るのは若松だ。休日の朝だから、都内は交通量も少なくて快適である。車が日比谷に差し掛かると若松が言った。
若:「ねぇ、Yくん達にオミヤゲがあるんだけど、ちょっと職場によってもいい?」
静:「もちろんいいよ。通り道だし」
若松は職場前の道路に車を停止させると、建屋に入って行った。しばらくして戻ってきた彼は、デカい透明のビニール袋を抱えている。
若:「はい、これ。お土産…南極の氷!」
Y:「えー、ありがとうございます!!でも、どうしたんすか?」
若:「職場の人が南極の越冬隊からもらってきたんだよ。ペンギンのオシッコも入ってるから。」
Y:「…」
この南極の氷は、実際に越冬隊から送られてきたものである。オミヤゲに南極の氷を用意するとはさすがは若松!
しかも用意がいいことに、彼は移動中に氷が溶けないように、デカいアイスボックスまで車のトランクに準備していたのである。
車は第三京浜を走って、やがて江の島に到着する。一通りの見物を終えると、運転を交代して、今度は鎌倉駅方面へと向かう。
静:「そろそろ鎌倉駅あたりだけど、鶴ヶ丘八幡宮でも寄ってく? 昼食を横浜中華街でとるんだったら、あんまり時間ないけど。」
若:「えぇー。八幡宮!? あんなのただの寺じゃん。大仏の方がいいよー」
静:「大仏なんて、ただの仏像じゃん。おまえが見たいんじゃないの?」
若:「オレは見たくなんかないって。でも、Yくん達は大仏の方が嬉しいって!」
静:「Yくんはどっちがいいの?」
Y:「僕はどっちでもいいです。でも来週、職場の試験があるから、お守りとか買いたいです」
静:「じゃあ、八幡宮だな。」
若:「えー、大仏がいいよー!」
静:「なんでだよ。Yくんが、お守り欲しいって言ってるじゃん。おまえが見たいんだろ!!」
若:「オレじゃないって。オレは見たくないよー!」
静:「そういえばさ。この前、『鎌倉の大仏を見ようと思ったら、駐車場がいっぱいで見れなかった』って怒ってなかったっけ?」
若:「…」
静:「やっぱり、おまえが見たいんじゃん。」
結局、車は若松の希望通り鎌倉の大仏へと向かった。嬉しそうな若松を見ると、なんだか自分がイイコトをしたような気にさえ思えてくる。しかし、大仏前に到着すると駐車場は満杯で、結局、車を停めることはできなかったのである。
悲しみをたたえた若松の横顔は胸を打つ。だがそんなことは気にせず大仏前を通過して、車は横浜中華街へと向かった。順調に進めば約40分ぐらいで到着するだろう。
途中、自販機で飲み物を買うために車を止める。ついでにトランクのアイスボックスを覗いた若松が言う。
若:「あのさー、南極の氷、溶けてきちゃってるんだけど、どうしようー」
静:「アイスボックスごとあげるんでしょ、ドライアイスでも入れておけば?」
若:「アイスボックスはあげないよ。氷だけ!」
彼は、Yくんがビニール袋を持ったまま秋田まで帰ればいいと思っていたらしい。それって、ふつーに解けるよね? なんでこいつは、何も考えずに”南極の氷”なんぞをお土産にするんだよ!
若:「ねぇー、どうするぅ? 溶けちゃうよぅー」
静:「なんでクール宅急便とかで送らなかったの? 持ち歩くから溶けるんじゃん。Yくん達が帰るまでに無くなっちゃうよ」
若:「えっ! クール…そんなのがあるの?」
静:「知らなかったの!? コンビニとかで受け付けてるよ。」
若:「コンビニいく!!! どっかにコンビニないか探してよ!」
何かに取り憑かれたかのようにコンビニ、コンビニとつぶやき続ける若松は、気味が悪かった。
横浜に到着した我々は、山下公園の前に車を停めると、中華街へと歩きながら途中にコンビニがないかを探した。若松が、ウンコかエロ本以外の目的でコンビニを探すなんてはじめてだ。
ところがこういう時に限って案外と見つからないもので、ようやく辿り着いた店は、中華街の裏手にある小さなファミリーマートだった。
店に入ると、若松は氷をもってレジに直行する。
若:「これ送りたいんですけど!」
若松はレジの上に、どんと氷が入ったビニール袋をおいた。びっくりしたのはレジの女性である。
だいたい宅急便というものは、箱詰めとかにして持っていくものであって、こんな風にいきなり氷が入ったビニール袋をポンと持ってくる人なんていない。
レジ係の二人の女性は、しばらく顔を見合わせていたが、やがて一人が叫びながら奥へと走っていった。
レ:「…て、てんちょうぅー!!!!」
残されたポリネシアン系のレジ係は、「こんなもん持ってきやがって!」とばかりに若松を睨んでいる。
若松を除く3人は、思い思いの方向を向きながら、”私たちはこの人の連れってわけじゃないんですよ”という姿勢をアピールした。
やがて奥から、イヤイヤそうに店長が出てきた。眉間にシワが寄っている。レジの上には、溶けだした氷がビニールの破れ目から漏れて、水の輪が広がりはじめていた。
店:「箱とかはないの?」
若:「ないです。ください!」
店長は鼻でため息をつくと、この男には何を言っても無駄だと判断したのか、余りモノの箱を用意して、自ら氷の箱詰め作業をキビキビと行いながら、若松に送付伝票を書くように指示をした。まさにサービス業の鏡のような店長と、デキの悪いお客の見本みたいな若松である。
ひとつのレジを占有してしまったので、隣のレジの列が伸びている。そこに並んでいる客は皆、好奇心丸出しで若松を見ている。
ようやく宅急便として形が整ったときには、レジの上は溶けた氷でびしょびしょだった。
それに気づいた若松がレジの女性に言う。
若:「ありゃ、濡れちゃってごめんさい。拭きます。」
そう告げるが早いか、彼はレジの女性の制止も聞かずに、レジ脇にあるティッシュ箱から、ティッシュを抜き取ってレジの上を拭き始めた。ときどき、「はぁー」などと息を拭きかけて磨く小技まで使っている。
レジ係:「あ…あの、もう結構ですから。ありがとうございます。」
レジ係は戸惑いながらも若松を止めるのに一生懸命だ。そして若松といえば、女性の気を引けたのが嬉しいのかさらに調子に乗りはじめた。
若:「あっ、ここ汚れてますね。ついでに拭いときますね」
今度は、レジの機械まで磨き始めた。それが終わると、さらにセロテープ台まで磨いている。放っておくと店中を拭きだしそうな勢いだ。店内のお客も何がはじまっているのかと不思議そうにレジを見ていた。
静:「もう、行くよ!」
ようやく店から若松を引っ張りだして振り返ると、レジ係の二人は心からホッとしたような顔で見送っていた。
店長とレジのお姉さんたち、迷惑をかけてすみませんでした…。
でもね、そのホッとした気持ちはオレもまったく同じでしたから。